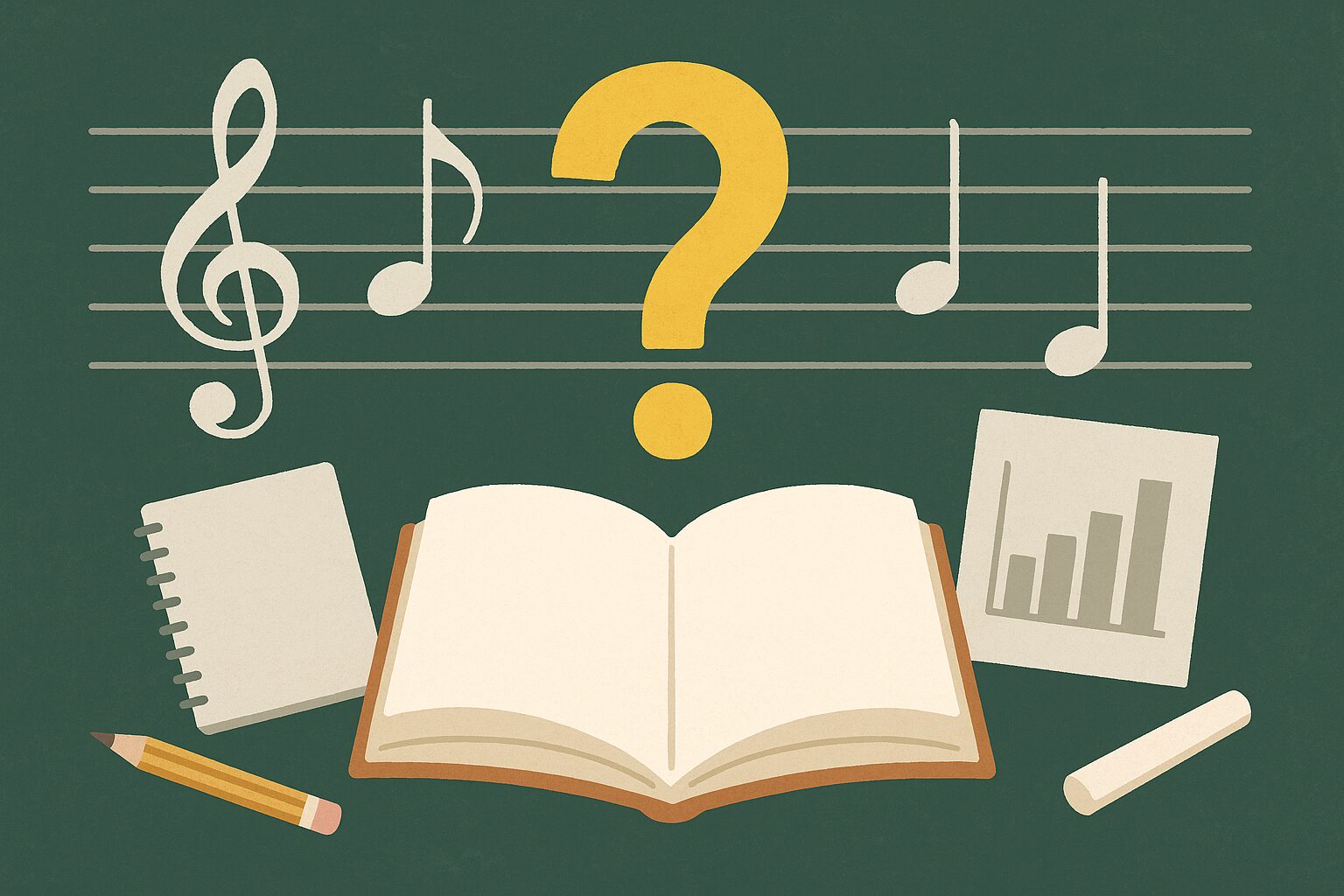私は、「何かができるようになる」ということは、「その良し悪しを理解できるようになること」と深く結びついていると考えています。たとえばスポーツの場合、サッカーではボールを上手に受け止めてコントロールする技術が重要です。ボールをやわらかく受け止め、自分が蹴りやすい位置に静かに置くことができるかどうかが、上達の指標になります。野球であれば、打つのが難しい内角低めのボールを、どれだけ強く遠くへ打ち返せるかが、実力を測る目安になります。
こうした「良し悪しの物差し」を伝えることが、学校教育の役割だと思うのです。なぜなら、物差しが明確であれば、子どもたちは自ら課題を見つけ、自主的に練習に取り組むことができるからです。
音楽の授業に欠けている「音楽の良し悪し」の話
では、音楽の授業はどうでしょうか?
みなさんは、優れた音楽とはどういったものか、理解していますか?
私自身、クラシック音楽の「良し悪し」というものを、大人になってから初めて知りました。
たとえばクラシックでは、「その曲が作られた当時の音楽をどれだけ忠実に再現できているか」を重視する考え方があります。たとえば、19世紀前半に活躍したショパンの時代のピアノは、現代のピアノに比べて音が軽やかで、響きも控えめでした。このため、演奏者はペダルを細やかに使ったり、メロディの流れを自然に美しくつなぐなどの工夫によって、繊細な表現を引き出していました。現代のピアノでショパンを演奏する際も、単に音を長く響かせるのではなく、当時のように一つ一つの音の表情や間の取り方に細かく気を配るといった再現の努力が求められるそうです。
こういった「物差し」を、なぜ学校の音楽の授業で教えないのでしょうか?
私はこの話を大人になってから知り、非常に衝撃を受けました。音楽を専門的に学んだ人たちにとっては常識だそうです。しかし義務教育では、ほとんど教えられていないのではないでしょうか。
上で述べたのはあくまでクラシックの話ですが、J-POPなど現代音楽の授業においても、「何が物差しなのか」はほとんど教えられていません(個人的な経験に基づく経験です)。これは主体性を育てるという学校教育の方針と矛盾しており、大きな問題ではないでしょうか。
物差しなき指導が生む徒労感
現状の音楽の授業では、「大きな声を出しましょう」「お腹から声を出しましょう」「音程を合わせましょう」といった、表面的な技術指導に偏っていると感じます(個人的な経験に基づく見解です)。
しかし、それ以前に、音楽における「良し悪しの基準」や「表現の奥深さ」を伝えるべきだと私は思うのです。
物差しを知らないまま練習するのは、地図を持たずに旅に出るようなものです。方向がわからなければ、努力のしようがありません。
教師の対応が示す、教育の根本的な問題
あるとき、私は音楽の教員にこの疑問をぶつけてみました。すると、その教員は次のように言ったのです。
だったら、あなたが努力して理解できるようになればいいじゃない。あなたの個人的な問題でしょ
しかし、私はこの意見には賛同できませんでした。
試しに職員室で、他の科目の先生方にも尋ねてみました。私の話したようなクラシック音楽や現代音楽の物差しを、学校教育だけで学んだ人は一人もいませんでした。私の親や友人も同様です。
これは、個人の努力不足の問題ではなく、学校教育そのもの、カリキュラムの問題だと私は考えます。
努力では埋まらない教育の責任
「努力してできるようになればいいじゃない」という指摘も、的外れです。
私はこれまでコスト(=時間)を支払ったにもかかわらず、対価である教育サービスが不十分だったと指摘しているのです。そこからさらに新たなコストを支払って再教育を受けたとしても、最初の教育が適切だったとは言えません。
たとえば、あなたが200万円払って買った車が、本来100km/h出るはずなのに、80km/hしか出なかったとします。販売店に異議を申し立てたところ、「気に入らないなら、別の販売店からもう一台買えばいいじゃないですか」と言われたら、納得できるでしょうか?当然、できないはずです。200万円を出した時点で、適切な車(100㎞/h出る車)を手に入れることができるはずなのに、販売店のいうとおりにすれば、合計で400万円支払ったことになるからです。本来のコストよりも多く支払って、対価を得たとしても適切な取引とは言えません。
教育においても同じことが言えます。仮に私が自力で学び直して音楽の物差しを理解できるようになったとしても、それは私が多くのコストを払って対価を得ただけのことであり、学校の教育サービスが十分だったことにはなりません。
生徒の「時間」を預かるという重い責任
もし先生が、「あなたの言っていることは理想が高すぎる。実際に音楽の授業だけで音楽の物差しを理解するのは難しい」と答えたのであれば、私は納得できたかもしれません。
しかし、私の場合は「努力不足だ」と片付けられてしまいました。このような先生の姿勢は、あまりにも無責任だと感じます。
生徒は、時間という貴重なコストを支払っています。教師は、その時間を預かる責任を自覚しなければなりません。
そのうえで、授業の中で「物差し」や「わかってもらいたいこと」を明確にし、生徒に伝える努力をするべきです。私はそう強く思います。